【農業のDX×地域再生×みどりの食料システム戦略×食とエネルギー】第2回ウマバSDGsアカデミー(雲海塾)
- 勇起 床桜
- 2024年3月31日
- 読了時間: 9分
更新日:2025年3月16日

第2回の雲海塾には、徳島文理大学の学生11名と、企業や自治体の方22名、合わせて33名が参加しました!
第2回ウマバSDGsアカデミー2024(雲海塾)プログラム内容
10月25日(金)
【第Ⅰ部】 講演
13:00~13:30「みどりの食料システム戦略」徳島県農林水産部長 中藤直孝 氏
13:30~14:10「食とエネルギーがまつわる未来」(株)アグリツリー代表取締役 西光司 氏
【第Ⅱ部】 講演
14:20~15:00「スマート農業の現在と未来」(有)樫山農園代表取締役 樫山直樹 氏
15:00~15:40「農業DXへの挑戦」スタンシステム(株)代表取締役 真鍋厚 氏
15:40~16:20「ソーラーシェアリング最前線」(株)シーラーソーラー取締役 小西豪 氏
【第Ⅲ部】 トークセッション
16:30~17:45 「ウマバプロジェクトに期待すること」
(株)徳島大正銀行取締役会長 吉岡宏美 氏
(一社)三好みらい創造推進協議会代表理事 丸浦世造 氏
(株)河村電器産業課長 高橋徹 氏
(株)村田製作所シニアマネジャー 佐藤和三 氏
(株)国際航業デジタルエネルギーグループ長 白川紳吾 氏
【第Ⅳ部】
18:00~ 交流会
10月26日(土)
【第Ⅴ部】 体験
7:00~8:30密厳寺「護摩焚き体験」
9:00~11:00カードゲーム「2050カーボンニュートラル」
11:00~11:30まとめ
11:30~昼食・解散
【第Ⅰ部】 講演「食とエネルギーがまわる未来」講演「みどりの食料システム戦略」徳島県農林水産部 中藤直孝 氏

徳島県農林水産部長 中藤直考さんから「みどりの食料システム戦略」での具体的な取り組みについてお聞きしました!徳島県みどりの食料システム戦略の計画における「調達」、「生産」、「加工・流通」、「消費」の各課程において環境負荷低減に資する取り組みについて学びました。
私達と特に身近な食料問題の1つとして食品ロスが挙げられますが、そういった食料の過剰な廃棄を防ぐ取り組みとして、「フードドライブ」や「フードバンク」などがあるということも学びました。
その他にも様々な取り組みがされており、「ソーラーシェアリング」や「サステナブル林業の実現に向けての取り組み」、「純・徳島産 サツキマス養殖」など幅広い観点から活動が行われています。
このような活動を通して、より多くの人に現状を知ってもらい、限りある食料・資源の正しい使い方を理解してもらうことでこれからの未来を私達1人ひとりの手で守っていくことが出来ると思います。

レポート担当:徳島文理大学 山本将輝
講演「食とエネルギーがまわる未来」(株)アグリツリー代表取締役 西光司 氏

(株)アグリツリー代表取締役 西浩司さんの講演では、「食とエネルギーがまわる未来」について具体的な取り組みをお聞きすること出来ました。ソーラーシェアリングとは、「農地の上に、簡易に撤去できる支柱を立てて、その上に太陽光パネルを設置して、太陽発電と農業を同時に行う仕組み」のことです。
日本では環境省が2050年を目標にカーボンニュートラルをゴールに掲げており、脱炭素先行地域を設けて2030年までに先行事例を作ることを目指しています。そこで、ソーラーシェアリングが重要な役割を果たしており、現在注目されていることがわかりました。
その地域の農業の課題を解決しながら、再生可能エネルギーをどう生み出すかについて、ソーラーシェアリングが注目されているそうです。
これまで、ソーラーシェアリングという言葉を聞く機会がありませんでしたが、講演を聴くことでソーラーシェアリングがいかに必要なのかを知るきっかけなりました!
レポート担当:徳島文理大学 山脇陽貴
講演「スマート農業の現在と未来」 (有)樫山農園代表取締役 樫山直樹 氏

樫山農園代表取締役 樫山直樹さんから「スマート農業の現在と未来」についてのお話を聞きました。樫山農園さんは小松島市や阿南市、徳島県内を中心にオランダ式スマート農業を行っていて、化学的有機農業を取り入れています。
20年後に農園の未来として「2度上昇すれば1億8900万人が飢餓に陥る」「3度上昇すると普通の雨の日が無くなる」「食料が原因で戦争に」が起こると仰っていました。
樫山農園さんが掲げる経営理念として「樫山農業で世界を幸せ」があります。
樫山農園さんでは農地の管理をすべてデータで行っていて作業や時間の管理を自動で行っています。まさにこれからの時代の農業でありDX化だと思います。次は実際に樫山農園さんにお邪魔させていて最先端の農業を見学したいと思いました。
レポート担当:徳島文理大学 山脇陽貴
講演「農業DXへの挑戦」 スタンシステム(株)代表取締役 真鍋厚 氏

(株)シーラソーラー取締役の小西 豪さんから「ソーラーシェアリング最前線」について具体的な取り組みをお聞きしました。(株)シーラソーラーでは、ソーラーシェアリングの普及に向けた取り組みをされています。ソーラーシェアリングとは、営農を維持しながら発電を行うシステムのことで、現在、日本では約5000ヶ所存在するということを学びました。
また、ソーラーシェアリングには、場所や環境に応じて様々なモデルを作ることが出来るということも学びました。例を挙げると、台風などのその地域の災害の特徴に合わせたモデルや、企業課題解決モデル、地域課題解決モデルなどです。
このソーラーシェアリングは、フェーズフリーでもあり、災害時には電力供給の機器としても役立たせることが出来るということにも驚きました。夜にウマバスクールコテージ横にあるソーラーシェアリングを見た時にライトが綺麗で、見た目もいいなと感じました。
レポート担当:徳島文理大学 村上大斗
トークセッション「ウマバプロジェクトに期待すること」
(株)徳島大正銀行取締役会長 吉岡宏美 氏
(一社)三好みらい創造推進協議会代表理事 丸浦世造 氏
河村電器産業(株)課長 高橋徹 氏
(株)村田製作所シニアマネジャー 佐藤和三 氏
(株)国際航業デジタルエネルギーグループ長 白川 紳吾 氏


トークセッションでは、「ソーラーシェアリング事業におけるウマバモデルの意義と課題解決」や企業の取り組みについてお話していただきました。SDGsや再エネなど、環境保全に取り組む企業の方のお話を聞くことができ、企業が環境問題に対してどのように向き合っているのか、取り組みが企業にどのような影響を与えるのかを知ることができ、学びあるものとなりました。以下、6名のお言葉を抜粋して紹介します。
「最大の課題は人口減少や大規模災害である。ウマバでは自立可能なモデルを作りたいと考えている。」(丸浦さん)
「再エネをどんどん投入し、CO2の排出を減らす取り組みの中でうまく自社の商材を利用し、その取り組みで生まれたものを社外にも提案していくという高循環を生みだしたいと考えている。」(佐藤さん)
「現在、自治体は防災減災を重視している。まずはライフラインが何も使えなかった場合どうするのかを考えるべきではないか。自治体は中山間の限界集落が防災減災の対策をできるよう後押しをすることが1番大切だ。」(白川さん)
「EVの電力を他の場所に持っていけるようにすることで災害時にも使える価値創出ができないかと考えた。しかし、自治体の協力を得るにはより平時の利用価値を高めなければいけない。電力を持ちながら人とエネルギーを移動するという価値創出が重要になってくるのではないか。」(高橋さん)
「山間地域の農業も環境がどんどん変わっている。企業も環境の変化に合わせて事業をどう変えていくのか考えなければならない時代にある。」(吉岡さん)
「官と民がきちんと連携しなければならないがバランスを取るのが難しく、そこが問題である。ウマバスクールコテージのような例はまさに官民連携(PPP)である。」(小西さん)
トークセッションを終え、ウマバプロジェクトにはまだまだ多くの課題が残っていること、改めてこのプロジェクトがたくさんの方々の尽力の下で行われているということを実感しました。また企業が現在行っている取り組みや、企業側から見たウマバプロジェクトについてのお考えを聞くことができ、これからの活動においても非常に参考となる貴重な時間を過ごすことができました。
レポート担当:徳島文理大学 樫本由衣
ウマバ交流会

交流会では立食パーティという形で今回のウマバプロジェクトに参加してくださった企業や行政の方々が講義では時間の都合上聞くことが出来なかった質問や個人的なお話をしながら地元の食材を使った料理を楽しみました。
交流会の時間の中で将来や大学生活について、アドバイスや有益なお話を聞かせて頂きました。大学の授業を受けているだけではなかなかこのような機会は無いので、とても貴重な体験でした。
レポート担当:徳島文理大学 松本千紘
~2日目~護摩焚き体験&カードゲーム「2050カーボンニュートラル

徳島県三好市池田町にある四国三十六不動霊場第五番札所の密厳寺にて護摩焚き体験をしました。
寺内にある大不動堂という式場に入ると、濃い白檀の香りがしました。儀式が始まる前に、参加者の方々が護摩札に名前と願い事を書き、回収していただいてから、僧侶から儀式に唱える「六波羅蜜修行次第」本をもらってから、正式に始まりました。
経文を唱えるのをはじめ、そして和太鼓も加わって、願い事を記された護摩札は途中真ん中に置いてあったお護摩の火にあてて、約1時間程度で儀式が終わりました。
今回の護摩焚き体験は神秘にして貴重な経験ができたと思います。密厳寺の一夜で立てられた伝説も興味深く感じました。
カードゲーム「2050カーボンニュートラル」
(左)ゲーム終了後のカーボン・マップ (右)所持資金の変動がわかる表
10月26日に開催された雲海塾にて参加者の皆さんとカードゲーム「2050カーボンニュートラル」の体験会を実施しました。カードゲーム「2050カーボンニュートラル」とは、参加者が与えられたゴール条件達成に向け行動した場合の2050年での地球環境や経済をシュミュレーションするゲームです。最初は参加者間でゴール条件が異なるため、足並みが揃わないこともありましが、回を追うごとに、チーム間での活発な意見交換ができました。
最終結果として、過去の雲海塾で最も多い6チームが目標達成に成功しました。これは「温室効果ガスの削減」や「排出量削減」など共通のゴール条件を持つチーム間での積極的な協力や資金の交渉が行われたことが大きな要因だと感じます。ゲーム途中までは、社会全体での温室効果ガス量は減少していたものの、終了時には増加してしまい、環境と経済のデカップリング達成とまではいきませんでした。ゲーム終了後は、チームごとに感じたことを共有し、意見を深めました。
今回のゲームを通して、「個人としてだけ・組織としてだけ」ではなく両方の視点から同じスピード感で取り組むことが重要だと感じました。今回の参加者の皆さんは、カーボンニュートラルを目指す組織としての一面も、エネルギー消費者の一面も持っています。一人ひとりが、ゲームでの学びを日常で実践することを心がけていければと思います。
レポート担当:徳島文理大学 内田隆太郎
第2回ウマバSDGsアカデミー2024:全日程を終えて
雲海塾に初参加ではないのですが、今回の雲海塾への参加も含めて、大学に通うだけではできないような貴重な経験が出来ていると何度も実感しています。
企業の方々の講演に加え、私たちゼミの活動の一環としてカードゲーム「2050カーボンニュートラル」の開催もさせていただきました。前日の交流会に加えて様々な方々と交流の機会がある雲海塾では、初めての経験ばかりですが、私自身の新たな学びに繋がっていると思っています。来年度からは就職して働き始めますが、この雲海塾での経験を私自身の学びとして頑張っていきたいです。





























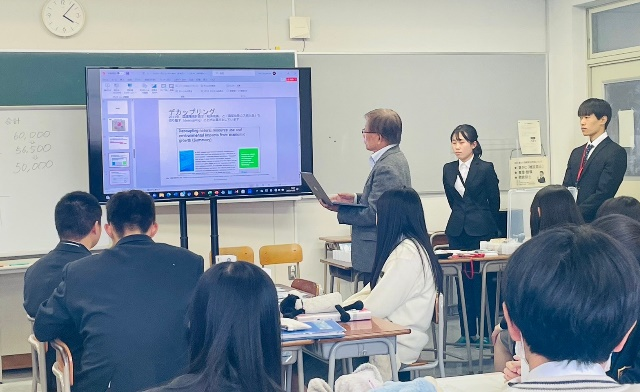
コメント